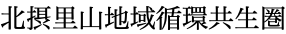右近 宣人(うこん のりひと)氏
一般社団法人Re-Generation代表理事/
関西電力ソリューション本部 開発部門 事業創出グループ
1999年大阪府生まれ。学生時代、NPO法人en-courage本部にて、経営者として事業開発・組織づくりに取り組む。
2022年、関西電力株式会社に、新ビジネス創造コース1期生として入社。
並行して、2023年6月一般社団法人Re-Generationを設立し、代表理事に。国内外で「次世代×産官学民」をテーマに、世代間連携の仕組み作りを行う。大企業で新規事業開発をしながら、起業家としても活動をしており、「大企業と起業の両方という第3の働き方」に挑戦している。
 兵庫県は2025年度に地域循環共生圏を次世代とともに活動するフィールドとすべく「里山・里海環境リーダー育成プログラム」に取り組んでいます。
兵庫県は2025年度に地域循環共生圏を次世代とともに活動するフィールドとすべく「里山・里海環境リーダー育成プログラム」に取り組んでいます。
県とともに本プログラムを運営する一般社団法人Re-Generationの右近宣人代表理事にお話をお伺いしました。
ーよろしくお願いします。
「世代間連携」が事業のキーワードですが、大学時代に何か気付きと言いますかきっかけのようなものがありましたか
よろしくお願いします。
私は大阪府豊中市育ちなんですが、父の実家が近い、佐賀大学経済学部で大学生活をスタートしました。
その後、関西に帰りたかったのもありましたが(笑)、大きくは経済学が課題や解決策を数字に重きをおいて考えることにすごく違和感を感じるようになりました。もっと人肌な解決策、社会全体の解決策を作るには、経済学的視点と法学的視点の両方から検討する必要があるのではと思い、3年次に神戸大学法学部に編入し、これからの社会に求められる法律のあり方などを学びました。
そう思い立った原点は、私が小学生の時に母親がボラティアで孤児院に子供達に英語を教えにいっており、そこに一緒に連れられた時での気付きです。”
恵まれない子供達”と”恵まれた子供達”がいて、子供なりに「その違いってなんだろう?たくさん議論されているのに解決されていないじゃないか。」と思ったのが根本のきっかけかなと、今振り返ると思います。
ー事業化のきっかけは
行政を学ぶ中で、より社会に積極的に関わる方法として「起業」を考え始めたことです。
特に、神戸大学在学時に、IGESさんと連携して実施開講されていた脱炭素社会に関する授業に参加したことが大きなきっかけになりました。
ただ、「起業」といっても私自身、デザインやプログラミングができるわけではありません。ただ、経済学・法学などさまざまな分野を、さまざまな人と学んできましたから、多様な人が集まって、議論することに価値はあると信じていました。
そこで、大人世代の人とZ世代が集まり、未来について議論する場を設けるワークショップをすることは何かしら社会解決に活かせる有効で面白い手法だな、自分に向いてるなと直感しました。
より社会に求められるワークショップをやりたい!と思い、IGESの講師の方に相談したところ、神戸で三宮再整備事業が具体化して来ているからこれをテーマにしてみたらとアドバイスいただき「これだ!」と動きました。

(参考:【Z世代と考える未来都市_神戸市×神戸大学×IGES】Z世代と神戸三宮の未来をデザインする。 「未来社会デザインとカーボンニュートラル」)
その時は、「大学生を集めて三宮再整備事業についてカーボンニュートラルとウォーカブルをテーマにワークショップを開催しますので、当日お越しいただけませんか?」とこちらから神戸市にメールでアタックしました。形を作ってからアプローチしたのがよかったと思います。
私は当時学生が中心となって運営する日本最大のキャリア支援団体(NPO法人en-courage)の経営に関わっていました。数百名の学生の自己分析のお手伝いをしており、Z世代のニーズ掘り起こしに関してはかなり自信がありました。また、多くの学生団体との関係もあり、ワークショップが実現しました。
このワークショップでは色々なアイデアが出ましたが、面白かったのが「脱炭素って分からないよね」という視点でした。何かモニュメントがあって今の脱炭素の割合、緊急性、危険度みたいなものが色が変わって見えるようにしたら、、みたいなアイデアが面白かったですね。
ワークショップ自体は成功裡に終わり大変高い評価を受けました。
その時に、ワークショップって政治参加のひとつの手法じゃないかなと感じました。投票だけじゃない自分の意見を政治に反映してもらう反映させる手法だなと。パブリックコメントと違った深掘りの効いた民意の反映の仕方じゃないかなあと、これ育ててみようと私は熱狂(笑)しました。
企業においても、企業経営・商品開発により積極的に若者が関わることができる仕組みがあると面白いなとも思うようになりました。
この成功をベースに多くの自治体、企業からお声かけをいただけるようになり、受け皿として作ったのが一般社団法人Re-Generationです。
ータイミングって大きいですね。Z世代とは?と聞かれたらどう答えますか
デジタルネイティブなど呼ばれていますが、端的には「未来の市場」「未来の意思」の一つのコアな「塊」だと思います。
その大きな塊が、「どういう社会意識をベースにしているか?」「どのように考える傾向にあるか?」を、行政や企業の施策に反映することで、より満足度の高い社会が生まれると思います。
あくまでも個人個性が満足を覚えるのであって世代で括っても、、、という意見はあると思いますが、世代が持つ通底する「何か」、例えばスマホが気が付いたらあった使っていた世代の持つ考え方があるわけなので、その考え方を社会に生かすことは大切だと思います。
多くのワークショップを通じて、次世代には「次世代1.0」と「次世代2.0」があると感じるようになりました。
「次世代1.0」は、初めて出会ったSNSに、自分をどうよく見せるかどう見せるかを追求したモアな世代かなと。
「次世代2.0」は、スマホです、SNSです、デジタルです、ネットです、に飽きてきていると思います。「もおええやん」みたいな。企業側もSNSでこんな発信していますではなく、ワークショップで情報共有していますをアピールすることの方が効果的だとお話しされていました。「私たちはSNSじゃないコミュニケーションをしています」をSNSで伝えるとかですね。
ワークショップをやると「回覧板がやりたい、近所の祭りをやりたい」という話が出たりします。今は対面が旬だと思います。またアナログに戻ってきてるんでしょうね。
(参考:2024年度 「社会価値創造型企業 NECと考える、2030年の自分と未来社会」)
ー今目指している形は
先ほどお話しした「対面で会話して問題解決していくこと」を進めていきたいと思います。
世代はこう考えていると言っても、大きなインタビューの母数を作ることは私たちにはできません。小さな会社ですので、Z世代に特化して一人一人のディープインタビューを積み重ね集めて、一般化した時の未来予測をして行くことが強みだと思います。
Z世代という若者たちと世代の離れた世代の違う人たちとが出会う場をデザインし、自分たちの考えをぶつけ合い、違いに気が付くことで、新しい何かが生まれます。「未来にワクワクする」そんな場作り、コーディネーションしていきます。
今回の「里山・里海環境リーダー育成プログラム」では、兵庫県環境部の地域循環共生圏に若者を参画を促したいという思いを、人材育成をベースにワークショップ、フィールドワークの中で具現化したいと考えています。何かをしたいと思う若者は多いですが、若者であるが故に現場を見ることができないという課題があります。今回は、北摂里山地域循環共生圏を中心とする「日本一の里山・北摂里山フィールドパビリオン」というフィールドを存分に知ってもらえるワークショップになるので、今からワクワクしています。
ー最後に右近さんの未来像は
踊り続ける人生を送りたいです(笑)。
このような人になりたい!という像はありませんが、色んな人に出会い、色んなことを経験し、未来を創り続ける人生でありたいです。
ーありがとうございました!
ー考えてみると私自身Z世代とこんなにお話ししたことないなと気付きました。
ー社会自体は世代がグラディエーションに階層化しているので、
なるほど、離れた世代と話す機会ってあまりないですよね。
ー次回はゆっくり飲みながら、、これはZ世代にはNGなんでしょうね(笑)。
ー楽しく気付きの多いインタビューでした。ありがとうございました。
T.Mi