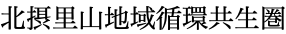今西 良拡(いまにし よしひろ)氏
菊炭本家 今西家
「日本一の里山」を支える大きな存在である「菊炭本家 今西家」。現当主の今西 学さんのインタビューから5年が経過しました。この5年間日本も里山も気候も大きく変動したように思います。
今回は、この今西家を継承する25歳、まさに次世代の今西良拡氏に移ろいゆく里山と次世代への思いをお聞きしました。
ーよろしくお願いします。私自身サラリーマンしか知りませんので、「家業」のイメージがありません。小さい時からどのように関わってどのように感じておられましたか
よろしくお願いします。
日常の中に仕事がある感じでした。小さい時からいつも身近にあるものだったので、その中で遊んでいた感じです。山に作業に一緒に行くんですが、それも遊びで山に行く感じですね。中学生の時はそれが手伝いに自然に変わりました。
高校も大学も加西市にあります農業系の学校に行きました。高校は普通校も考えていたんですが、たまたま友達が畜産に行くという話で、じゃあとオープンキャンパスに行ったんですが、ここも面白そうだと入学してみると、なんとその友達は入っていませんでした(笑)。でも面白かったですし、農業大学校も寮生活で楽しかったですね。卒業して、炭焼きの仕事に入りました。自分では、全て自然な流れだったと思っています。
ー今西さんの一年のサイクルを教えていただけますか
菊炭のシーズンは紅葉が終わる12−1月に伐採は始まります。
その前の11ー12月に伐採する原木の林の下草刈りをします。この下刈りでは、NPO法人ひょうご森の倶楽部の皆様に大きな力を発揮していただいています。
伐採して玉切りして1月半ばから窯に入れて焼きます。窯は7−8日で出し入れします。この伐採ー玉切りー炭焼きを同時に繰り返している感じです。切り口から新芽が萌芽しますので、伐採は4月には終わっています。全部の材を焼き終える5月くらいまで炭焼きを続けます。4月の半ばから畑が始まって5月のGWから夏野菜が始まって、5月半ばに田植えがあり、農作業に追われます。同時に炭の出荷は続いていますが、メインは冬になります。夏場はお湯を沸かすための炭ですが、冬場は茶室を暖めることも必要になりますので、秋口から出荷が増えます。その時期に重なるように稲刈りがありますので、なかなか追いつかない状況です。そして次の下刈りが始まります。
ー卒業されてお仕事に入ってからどのような変化を感じておられますか
鹿の食害による変化です。今振り返ると、ちょうど大学に入った頃に鹿の食害が急激に増えました。
その時期から食害を防ぐために2メーターくらい手が届く腕が伸びる範囲で一番高いところで木を切り始めました。これはその後の炭焼きを考えると大きなターニングポイントになりました。単純に低いところで切っていたのに2メーターで切りますから単純に2メーター分ロスが出ます。作業も大変になりましたから、原木の伐採が非常に難しく効率が悪くなってしまったんですね。
当時祖父(今西勝氏)が、これからは炭が足りなくなるとよく口にしていました。今考えるとその背景は、この鹿の食害による原木の減少と切り手の不足による炭の減産が供給不足を産むと予言していたように思います。その時期から懸命に菊炭の増産を進めストックしていたんですが、現在はそのストック分も底を突きそうな状況です。
鹿の食害の原因は気候変動も関わっています。私が小さかった頃と比べると雪が降らなくなりましたというか雪が残らなくなりました。結果的に雪が餌を覆って鹿が食べられず、鹿の自然減に繋がっていました。今はそんなことはありませんので、旺盛に食べていますし、合わせて猟師も減っていますので、頭数も大幅に増えています。また人の手が入っていませんので、木が歳を取っていきます。どんぐりが出来ませんよね。増えた鹿を山では養いきれまなくなって、今まで食べなかったクヌギの芽を食べ、さらに畑に降りてきます。里山の大敵ですね。電気柵も慣れると倒して入ってきますし、倒木で倒れた柵を超えてきます。大規模に効果がある獣害対策は今まだないと思います。バランスが崩れた結果ですね、頭が痛いです。
ーちょっと漠然としていますが、これからについてはどのようにお考えですか
原材料の確保の点からも製炭量については、色々工夫して現状を維持することは精一杯で可能だと思いますが、増やすことはちょっと考えにくいです。現状維持、増産に向けての大きな課題はふたつです。一つは原材料の確保、増産。もう一つは切り手の確保です。
気掛かりなのは、高切りした木がまだ伐採の時期を迎えていないことです。うまく萌芽し成長しているのか、初めてのことですので、そこが心配ではあります。ただ明るいニュースもあります。先程お話に出ましたNPO法人ひょうご森の倶楽部の皆様が15年前に植樹されたクヌギ林が伐採できるまでに成長し2年前に伐採しました。笹に負けたりして植樹してもなかなか成長しないんですが、凄い事だと思います。植樹もボランティアの皆様と力を合わせて続けていきたいと思います。
後は切り手ですね、切り方も特殊ですし、どうすればいいか今は思い付きません。
地域の高齢化から田んぼや畑を継承して欲しいというお声掛けは増えています。地域の次を考えると農業にも力を入れていきたいと考えています。
ー黒川で生まれ育って感じられる里山の良さは
ゆったりと過ごせるところですね。都会は分や秒の時計で時間が過ぎていきますが、ここでは日が上り落ちる自然の流れがいわば時計ですので、人間にはフィットしていると思います。自然の人間が機械の時計に合わせるのはしんどいですよね(笑)。
山が存在することで四季を身近に感じることが出来ます。四季という大きな流れの中で暮らしていますので、ゆったり自然に合わせて時が過ぎていきます。
黒川に移住される方は増えてきています。山の恩恵を感じる地域行事を通じて黒川の歴史、文化を共有することで里山の良さを知ってもらい、知るだけではなく里山で活動してもらって、一緒に里山を継承していきたいと考えています。これからもよろしくお願いします。
今回インタビューをとお話をいただきましたが、考えて動いているというよりも感じて動いているので、うまくお話しできたか心配です。ちゃんと記事になります?
ーありがとうございました。大丈夫です!!
ー農政全般から鹿の捌き方、畑の水の入れ方まで多岐に渡った横道も楽しいインタビューでした。
ー確かに最近は獣害の話をよく聞きます。
ー対策は力技になりますが、相手も弱い所を突いてきますので、大規模な地域全体の対策が必要になります。その音頭取りが一番大事です。今西さんのこれからの更なるご活躍に大いに期待しています。
T.Mi